自然と共に生きる、ダイフクのマザー工場の生物多様性保全活動

生物多様性保全への対応は、持続可能な社会を実現するための重要なテーマです。滋賀県下最大級の敷地面積を有し、豊かな自然環境に囲まれた滋賀事業所の敷地内には、これまで1,000種以上の在来種と70種以上の絶滅危惧種・希少種が確認されています。それらを守り、将来へ引き継いでいくため、当社はさまざまな活動に取り組んできました。2023年5月に改定した「ダイフク環境ビジョン2050」に、重点領域「自然との共生」を加え、事業活動が自然資本に与える負の影響ゼロを目指し、取り組みをグループ全体に展開していきます。
希少な生物が生息するダイフクのマザー工場
滋賀事業所がある滋賀県日野町は、東に鈴鹿山脈、西に琵琶湖、町内には標高1,110mの綿向山(わたむきやま)があり、森林や湿地、ため池、水田が多く見られ、多様で豊かな自然が残る場所です。敷地面積が約120万m2(東京ドーム約26個分)にも及ぶ滋賀事業所は、当社のマザー工場としてものづくりを集約し、約3,000人が働いています。広大な敷地の中で独自の生態系が育まれ、絶滅危惧種などの希少種を含めさまざまな生物が生息するのが大きな特徴です。

当社グループは2011年に「ダイフク環境ビジョン2020」を策定し、他企業に先駆けて環境への取り組みを実施してきました。日野町では、開発や里山の荒廃、外来種の侵入などによる地域の生物多様性の低下が見られる中、当社は2014年に滋賀事業所で「結いプロジェクト」を立ち上げ、事業所内の緑地を活かして本格的に生物多様性の保全活動を開始しました。活動には従業員が携わることで環境への関心を高めています。こうした活動が評価され、これまでに「緑化優良工場等経済産業大臣賞」「しが生物多様性大賞」などの受賞歴があります。
「ダイフク環境ビジョン2050」の2030年環境目標ではKPIを設定し、環境課題の解決に向けた取り組みを各国・地域の現地法人にも展開します。「自然との共生」に関するKPIでは、主要拠点(従業員数100人以上)における生物多様性保全活動実施率を100%、サステナビリティアクション年間延べ参加者数を3万人としています。
ヤマトサンショウウオは、保全のシンボル
滋賀事業所で生物多様性の保全活動をスタートするにあたり、2013年に事業所内全域の生物生態系調査を実施し、その結果、数多くの生物(写真)が生息していることが分かりました。これまでに1,000種以上の在来種と70種以上の絶滅危惧種・希少種※が確認されています。
- ※環境省、滋賀県のレッドデータブックに掲載されている種。
-

ニホンイシガメ
-

ハヤブサ
-

キキョウ
保全活動を支援していただいている株式会社ラーゴ(滋賀県近江八幡市)の自然再生・活動支援室長・牛島釈広(ときひろ)様は、滋賀事業所に多種多様な生物が生息している要因について「さまざまな自然環境がある上に、除草剤を使わずに人力で草刈りを行うなど、ひと昔前の里山の管理に似た保全であることが考えられます」と話します。

ヤマトサンショウウオの成体。全長70~120mmの小型で、2~3月に産卵期を迎える
こうした豊かな生物多様性を保全するための「結いプロジェクト」は「保全」「楽しみ」「交流」「発信」をモットーに活動を展開しています。代表的な保全活動の一つがヤマトサンショウウオの保護・増殖です。ヤマトサンショウウオは環境省レッドリストで「絶滅危惧II類(VU)」に分類され、滋賀県でも希少種に指定されています。サステナビリティ推進部環境品質グループの三好順子は「2013年の調査で見つかったヤマトサンショウウオを保全のシンボルにと考えました。滋賀事業所内にある『結いの森』の中に保全池を造成し、保護・増殖を行っています」と話します。
事業所内での調査では生態系に悪影響を及ぼすアメリカザリガニなど外来種の生息も確認されました。そこでヤマトサンショウウオの卵を外来種などの外敵から守るために、保全池の中に設置した網かごへ丁寧に移し、太陽光パネルとエアポンプを使って空気を送り込み、酸素不足にならないようにしながら飼育。卵からかえった幼体は一部を保全池に放流し、残りは元の場所に戻します。一部の卵は滋賀県立琵琶湖博物館に「地域個体群の保全」を目的に提供しています。
三好は「取り組みを始めた当初は飼育が上手くいかなかったこともありましたが、専門家の助言を受けながら改善を続け、現在は安定して成体に育つようなりました」と話します。牛島様は「保全池に移植したヤマトサンショウウオが成長し、再び池を訪れ、たくさんの卵を産んでくれたことがとても印象に残っています」と振り返ります。
また、保全池があるこのエリアでは、樹木看板やデッキなどに間伐材を利用し、環境にやさしい活動を推進しています。
トンボは50種を確認、他社と連携し取り組みを推進
全国的に減少傾向にあるトンボの保全活動にも注力しています。事業所内では50種のトンボが確認されており、モニタリングを積極的に行い、生物多様性に配慮した緑地管理に努めています。また、滋賀県に拠点を置く企業6社と連携した「生物多様性びわ湖ネットワーク」を結成し、「トンボ100大作戦~滋賀のトンボを救え!」と題した取り組みを展開。各社で“推し”のトンボを決め、保全に取り組んでいます。



参加型イベントで従業員が考えるきっかけに
また毎年秋になると、従業員とその家族向けに自然観察会を開催しています。事業所内に生息している昆虫などを調査するほか、ヤマトサンショウウオの保全池の水を抜き、ヤマトサンショウウオを捕食する可能性がある生物を参加者が協力して採取し、別の場所に移します。
従業員とその家族が参加する自然観察会。ヤマトサンショウウオの保全地の調査も
事業所内で拾ったツルや松ぼっくりをクリスマスリースやコケ玉作りに使用するなど、自然の恵みを楽しむイベントも行っています。「イベントを通じて、従業員とその家族が生物多様性を意識した保全について考えるきっかけになれば」と三好は話します。
社外の交流として、近隣小学校の生徒を受け入れての社会科見学や、県内の環境団体や企業とともに、事業所内フィールドを使った交流会も開催しています。社内では、専門家を招いてのセミナーやシンポジウムで、自然環境保護や生物多様性保全について周知し、従業員の環境意識の向上に取り組んでいます。
楽しむ仕組みづくりを心掛け、活動の輪をグローバルに
生物多様性保全はダイフク1社でできるものではありません。外部との連携も重要です。トンボ100大作戦を展開する「生物多様性びわ湖ネットワーク」のほか、2015年に「一般社団法人 滋賀グリーン活動ネットワーク」の会員が立ち上げた「生物多様性と環境・CSR研究会」に参画し、多くの中小企業向けに生物多様性の基礎知識や最新動向を伝えるセミナーを開催し、交流の場を設けています。
サステナビリティ推進部副部長の山本剛広は「『ダイフク環境ビジョン2050』を改定し、従業員100人以上の拠点で生物多様性保全活動に取り組むという社内ルールを作りました。今後の課題は、滋賀事業所以外の各拠点で独自に行っている取り組みを仕組みの中で運用していくことです。どういった基準で何に取り組むか、具体的なメニューを2024年度に作成します。国内はもちろん、海外の現地法人にもルールを適用し、情報開示を進めていきます」と話します。
生物多様性保全活動に取り組む上で必要なこととして、山本は「面白くなければ興味は湧きません。また、メリットがあればさらに長く続けられるでしょう。こうした点を踏まえ、従業員に保全活動に、自主的に参加してもらうために、エコアクション制度※(現サステナビリティアクション制度)を始めました。今後も楽しみながら自ら考えて行動する仕組みを増やしていきます」と続けます。また、三好は「私自身、楽しみながら取り組まなければ活動は続けてこられなかったでしょう。情報を発信しながら、楽しむことを共有したいです」と話します。
当社グループは、これまで培った経験を次に生かしながら、活動の輪をグローバルに広げ、今後も生物多様性の保全に取り組んでいきます。
- ※2012年にスタートした従業員の自主的な環境活動にポイントを付与する制度。獲得したポイントはエコ商品などに交換可能。獲得した総ポイントの相当額を外部団体に寄付している。2023年から「サステナビリティアクション」に名称を改め、社会貢献活動にも対象を拡充。

牛島 釈広 様
株式会社ラーゴ
自然再生・活動支援室長
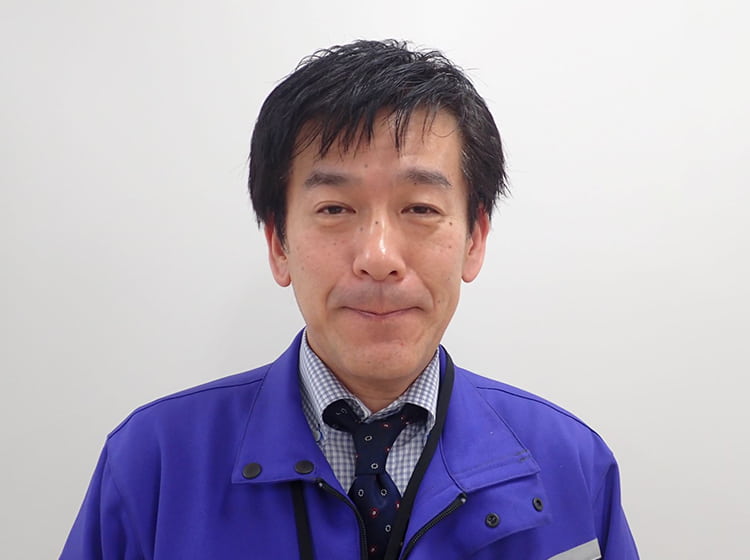
山本 剛広
株式会社ダイフク
サステナビリティ推進部副部長

三好 順子
株式会社ダイフク
サステナビリティ推進部環境品質グループ


