価値創造の源泉は「人」。グローバルで成長を続けるダイフクの人的資本経営とは

ダイフクグループにとって、人材は価値創造の源泉です。これからも「モノを動かす技術」で物流や生産現場などの社会インフラを支え、社会課題解決にも一層貢献していくために、どのようにして社員一人ひとりが最大限に活躍できる環境を整えていくのか。CHRO(Chief Human Resource Officer)でコーポレート部門長を務める取締役専務執行役員の田久保秀明に、ダイフクが推進する人的資本経営について話を聞きました。
ダイフクにおけるCHROの役割とミッションを教えてください。

ダイフクが実践する人的資本経営では、個人の集合体である組織の力と、組織を構成する個人の力を、それぞれ最大限に生かすことを重視しています。ダイフクは長年にわたり事業部制を敷き、業界に特化した事業展開でお客さまの課題解決に貢献し、成長してきましたが、人的資本の観点では人と技術・スキルが各事業部に固定化する傾向がありました。硬直化した組織では特定分野の専門性が身につく半面、年数を経るほどに成長が止まる恐れがでてきます。そこで全社的な視点で最高のパフォーマンスを発揮できるように、事業部制の良い面を継続しつつ、人材の流動化を図って、全社最適の人材マネジメントを目指しています。
全社最適の人材マネジメントの具体的な取り組みについて聞かせてください。
2023年度から、ダイフクグループの経営に大きな影響をもたらすキーポジション(主要幹部職)の特定と、そのポジションに求められる人材要件の明確化や後継者の育成に取り組んでいます。本部長クラス以上の上位幹部層は事業横断のメンバーで構成される委員会で、部長クラスの後継者は事業ごとの委員会で、それぞれ計画を策定しています。後継者候補が十分に確保できているポジションもあれば、確保が必要なポジションもあり、偏在も含めてデータの整備を通じて全社の人材を「見える化」し、部門の垣根を越えた最適配置を図ります。
それに伴い、これまでは各事業部でスキルを管理していましたが、全社共通の物差しとなる評価基準が必要になりました。事業ごとに求められるスキルが異なるため簡単ではありませんが、CTO(Chief Technology Officer)とも連携し、中期経営計画の最終年度の2027年までに形にしたいと考えています。将来的にはこの仕組みを一般社員にも広げることを視野に入れています。
また人材の流動化の観点から、新規事業の推進など会社が募集する分野で社員に活躍の場を提供する社内公募制度や、将来を見据えて自身の幅を広げるために一定期間他の事業・職種を経験できる社内出向制度も整備しています。
2030年の長期ビジョンで掲げている、ありたい姿の実現に向けた人材の育成や採用の考えを聞かせてください。
ダイフクは2030年の長期ビジョン「Driving Innovative Impact 2030」を掲げ、連結売上高1兆円の達成を目指しています。このありたい姿は、現在の延長線上の取り組みでは実現が困難なので、既存事業の拡充はもちろんのこと、新たな領域にも挑戦しているところです。そこではAIやデータサイエンスの活用が欠かせないことから、CTOが中心となり、役員から一般社員を対象に基礎的な研修を行うことに加え、選抜した人材に対してはより専門性の高いプログラムを用意し、全社員の10%をDX・AI人材へ育成する目標で取り組んでいます。
また、技術系人材の採用強化を目的に、東京と京都に研究開発拠点を新設します。ダイフクの技術部門は滋賀のマザー工場に集中しており、研究開発に興味がある学生にとっては希望の職務と勤務地とのミスマッチが生じるケースがありました。新設する東京の拠点「東京Lab」は全社横断的な技術開発を担い、AIやロボット、データサイエンスなどの専門分野を学んだ人材を積極的に採用して開発力の強化を図ります。京都の拠点「京都Lab」は、大阪や神戸からも通勤可能で、滋賀とも行き来しやすいアクセス性から選定しました。そこに事業部の開発機能の一部を移管します。従来は事業単位で建物が分かれていましたが、新拠点ではオープンなレイアウトにするなどによって事業の枠組みを超えた人材交流を促進し、各事業の技術力の強化につなげていきたいと考えています。
-

東京Lab内部のCG。開設は2026年1月予定
-

京都Labが入居する建物の外観。開設は2025年11月予定
これからのダイフクをけん引するリーダー人材はどのように育成しますか。
経営の観点を持った次世代のリーダー人材の育成を目的に、神戸大学と提携した約8カ月の養成研修を実施しています。ビジネススクールに準じたカリキュラムで大学の講師陣から経営学を学び、体系的に理解を深めた後、最終プログラムでは、社長をはじめとする経営幹部を前に新規事業案や既存事業の成長戦略を発表してもらいます。内容は一部変わりましたが、これは2002年から続いている制度で、私自身も受講しました。当時は各事業部から選抜された課長・部長代理クラスが対象でしたが、さらに早い段階から経営の意識を持つべきとの考えから、現在は対象を40歳前後の係長クラスに引き下げました。通常業務と並行して成果発表をまとめるのは容易ではありませんが、幹部候補として推薦された人材ですから、将来の会社を支える意識で臨んでもらっています。
グローバルの人材戦略についても考えを聞かせてください。

研修ではグローバルの社員が対話も行う
ダイフクグループのネットワークは世界に広がっており、24の国・地域に子会社があります。M&Aでグループ入りした海外子会社が多く、特定の事業領域に特化した組織構成となっています。そもそも企業風土や文化も日本とは異なります。そこで海外の社員にも経営理念をはじめグループ全体への理解を深めてもらおうと、各子会社から選抜した人材を集めた研修も実施しており、近年は毎年20名程度が日本に集まり、社長や各事業トップ、日本の幹部候補との対話などを行っています。ダイフクの社是「日新(ひにあらた)」は、常に改革の精神をもって進化し続けるダイフクの企業文化であり、強みでもあります。海外の人材に対しても「『日新』を世界共通にしよう」と伝えています。
また、事業のグローバル化を図るため、日本で海外の理系学生の新卒採用にも積極的に取り組んでいます。当初はコミュニケーション上の懸念もありましたが、技術には共通言語があり、優秀な人材は語学習得も早いので、日本に関心が高い技術系人材を採用し、入社前に日本語研修を実施しています。取り組みを本格化させた2019年度以降、直近の内定も含めて50名弱を採用しました。国別ではインドが最多で、インドネシアやマレーシア、タイ、台湾といったアジア圏が多くを占めています。
ダイフクで活躍できるのはどういった資質の人材ですか。
ダイフクは顧客志向と品質志向が強みです。時にはお客さまから難しい要望が寄せられますが、それに対して「できません」と言わずに「どうしたらできるか」を考え、ニーズに応えて品質にもこだわります。その結果、信頼が生まれ、継続したお取引につながっています。粘り強さはダイフクのDNAと言える部分で、社員に求める資質でもあります。
社員がダイフクでの仕事に熱意や愛情を持てるよう、給与水準の改善に積極的に取り組むとともに、福利厚生も含めて働きやすい仕組みづくりなどにも努めています。今後も「自分を成長させたい」という意欲を持つ方にとって最適な環境を整え、新卒・キャリア採用を問わず、向上心を持つ方を採用していきたいと考えています。そして社員一同、これからも現状に甘んじることなく、日々進化と変革を志し、「モノを動かす技術」でお客さまや社会の課題解決に貢献してまいります。
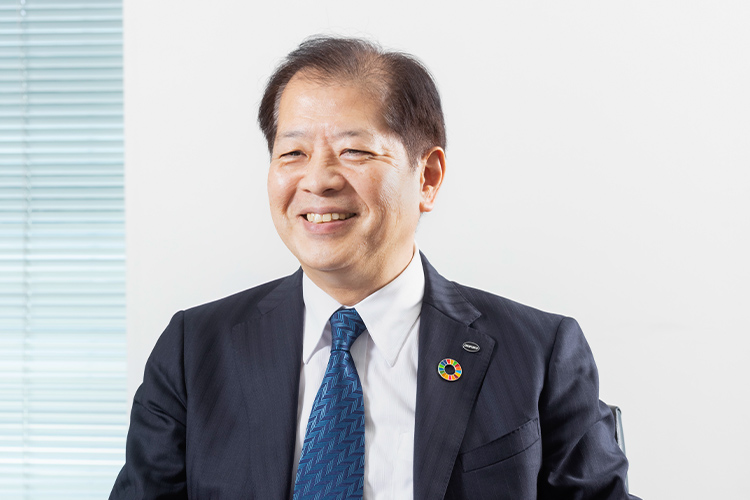
田久保 秀明
株式会社ダイフク 取締役 専務執行役員
CHRO(Chief Human Resource Officer)
コーポレート部門長
