ダイフク流課題解決ロボットによる自動仕分けで生産性向上を実現(株式会社ノジマ様)
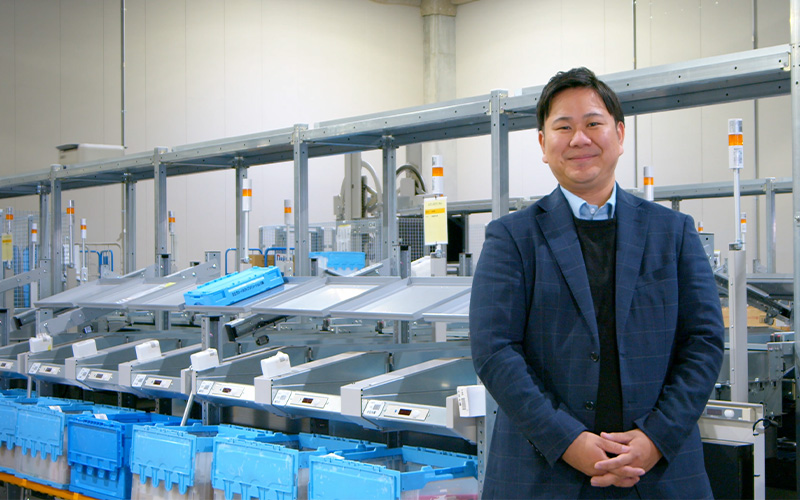
デジタル家電専門店を展開する株式会社ノジマ様(以下敬称略)。店舗への商品の配送などを担う埼玉県三郷市の三郷商品センターに、搬送ロボットによるピース品の仕分けシステム「SOTR-S(ソーティングトランスファーロボット-S)」を2024年10月に導入し、従来と比べて作業負担の軽減と作業時間の削減を実現しました。導入の狙いや効果などについて、三郷物流ソリューショングループでグループ長を務める丸山雄太郎様にお話を伺いました。
三郷商品センターの位置付けを教えてください。
当社は首都圏を中心にデジタル家電専門店を242店舗(2024年9月末時点)展開しています。以前は大黒(神奈川県横浜市)の物流センターで全店舗に対応していましたが、店舗数を年々増やす中で新たな拠点として、2022年に三郷の大型物流センター内に「三郷商品センター」を開設しました。東京外環道の三郷インターチェンジから約0.5kmの場所です。本センターがカバーするのは埼玉県、東京都、千葉県、茨城県の87店舗で、横浜よりも物理的な距離が短くなったことで配送効率が高まりました。
三郷商品センターではどのような商品を扱っていますか。

電池やSDカードのような小型商品から、テレビ、冷蔵庫、洗濯機といった大型家電まで、店舗で提供する全ての商品を扱っています。2階と3階の2フロアに分かれていて、2階ではメーカーから入荷された小型から中型の商品を店舗別・方面別に揃えて出荷しており、ダイフクのマテリアルハンドリング(マテハン)システムを導入して自動化・省力化を進めています。一方、3階では設置工事が必要となる大型家電の在庫管理や出荷などを行っています。
設置場所のスペースが課題、従来式のソーターでは収まらず
開業時点では、小型商品の仕分けは手作業で行っていたとお聞きしています。どのような作業だったのでしょうか。
メーカーから本センターに入荷された商品のうち、炊飯器や電子レンジなどの中型商品は、段ボールのままダイフクのコンベヤで仕分け・搬送しているのですが、電池などの小型商品は店舗別の出荷コンテナに人手で仕分けた後にコンベヤに載せる必要がありました。
具体的な作業としては、担当者は紙に印刷された各店舗のピッキングリストを見ながら必要な商品をピッキングしたあと、歩きながら出荷コンテナに記載された店舗名を目で見て確認し、商品を投入していました。この作業には6人で6時間ほどかかり、担当者からは「長時間歩くのが疲れる」「目視で目が疲れる」との声が上がっていました。作業にはヒューマンエラーも伴うため「精神的につらい」という方もおられました。大黒のセンターでは同様の声が上がったことを受け、2019年に小型商品の仕分けにスライドシュー式のピースソーターを導入した経緯があり、本センターでも導入を検討しましたが、希望する設置場所に収まらないなど、いくつか課題がありました。
そのような中でダイフクの担当者に相談したところ、ピース仕分けシステム「SOTR-S」をご提案いただきました。SOTR-Sは、担当者は投入口でバーコードを読み込んだ商品をロボットのトレイに載せるだけで、あとは商品を載せたロボットがレーン上を自走して、店舗別のシュートに自動で仕分ける仕組みです。経験が浅い方でも作業ができ、何より省スペースで多くのシュート数を確保できる点が魅力的で、現場と一緒に考え導入を決めました。
導入にあたってはスペースを重視されていたということですね。
そうですね。センター内にはすでに各種設備が配置されていることから、手作業で仕分けを行っていたスペースに収める必要がありました。SOTR-Sはロボットが走るレーンを上下に重ねた2階層ループ方式になっており、一般的な仕分けシステムと比べて上部の空間を有効活用し省スペース化を実現しています。シュートはスライドシュー式ピースソーターと比較するとはるかに多い62シュートを設置でき、限られた条件下で最大限に確保できたと思います。
スペースだけでなく、システム導入の社内決裁を得るためにはスライドシュー式ピースソーター以上の効果があるかどうかが大事なポイントでした。つまり、ミスなく仕分けることは当然として、作業人数と作業時間をさらに抑えられるかどうかです。

バーコードを読み込んだ商品をロボット上部のチルトトレイに載せる

ロボットが高速搬送

該当するシュートでトレイを傾けて仕分ける

リフターで上層を経由し、下層の商品投入口に戻る
また、大黒のセンターではメインのコンベヤとソーターは連結しておらず、その間を手作業で運ぶ負担が課題になっています。両システムの設置場所が離れていることに加え、メーカーが異なることもあり、導入当時は連結するという考え自体がありませんでした。
今回は設置場所も近く、また、せっかくダイフク製に統一するのであればと、同様の負担が発生しないようシステム同士を連結させることにこだわりました。一方で、店舗への商品の配送が滞らないようにするため、連結工事の際でもメインのコンベヤの稼働は止めたくありませんでした。稼働を止めることなく連結できる場所はないのか、ダイフクの担当者と議論を重ね、「ここしかない」というポイントを見つけることができました。実はこの連結を実現したことが社内の評価が特に高かった点です。
着工から稼働までは1カ月程度と想定よりも早く進みました。ダイフクはこちらの意図を的確にくみ取り、素早く対応していただけるので、助かっています。

商品が揃ったコンテナをコンベヤに移す

コンベヤで出荷待機エリアに搬送

ロボットは必要に応じて自動充電
作業時間を半分以下に削減、今後も現場の負担軽減を推進
導入したことによる効果を教えてください。
マテハンを導入する際には、安定稼働と生産性向上を大前提に考えています。安定稼働については、既設のメインのコンベヤの状況から問題はないと信頼していましたし、実際の稼働状況や仕分けの正確性にはとても満足しています。
生産性については、小型商品の仕分け作業にかかる時間を現在は5人で3時間と、半分以下に抑えることができ、手作業だった頃に比べて大幅に向上しました。社内調整には苦労しましたが、想定以上の効果が得られて良かったです。今後もDXによる自動化・省力化を進め、生まれた余力を別の業務や新たな挑戦に充てたいと考えています。
三郷商品センターでは今後どのようなことに取り組んでいきますか。
当社は、お客さまのニーズを引き出し、最適な商品を考え提供する「コンサルティングセールス」を独自の販売戦略に掲げています。従業員一人ひとりの活躍と成長が重要になることから、自社のメイン事業を家電量販ではなく「人材育成業」と位置付け、「出る杭は伸ばす」の方針で社歴や年齢、雇用形態に関わらず、全員にチャンスが与えられています。さらに、従業員が1人の経営者として考え、判断し、行動する「全員経営理念」を行動指針にしています。
このように従業員に主体性が求められる考えは、店頭のみならず全業務に貫かれています。マテハンの導入についても一部の役職者だけで決めることはなく、現場の担当者が問題を提起し、皆で考え、意見を出し合います。SOTR-Sの導入も現場の声がベースにあった上で、私が窓口となり進めてきました。
三郷商品センターは周囲に住宅が多く、徒歩圏内に駅もあるので、幸い人手が不足しているわけではありませんが、従業員の負担は引き続き軽減していきたいと考えています。次の課題は冷蔵庫などの大型家電の仕分けや搬送の自動化です。具体的に何をどう進めていくのか、現場の担当者と共に検討してまいります。

株式会社ノジマ
カスタマーリレーション部
三郷物流ソリューショングループ グループ長
丸山 雄太郎 様
2014年入社。店頭での販売を担当し、入社わずか1年で部門リーダーに就任。本社の人材育成グループや物流ソリューショングループを経て、2022年に三郷商品センターへ異動し現在に至る。
